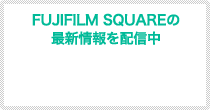- 写真展 FUJIFILM SQUARE(トップ)
- 写真展の鑑賞ガイド
- 「山と森の魅力を伝え続ける写真家」:水越武氏
「山と森の魅力を伝え続ける写真家」:水越武氏
【FUJIFILM SQUARE 写真歴史博物館企画写真展】水越 武 写真展 「真昼の星」
開催期間:
第一部 「天と地のあいだ・日本アルプス」 2016年2月2日(火) ~ 2016年3月31日(木)
第二部 「いのちの聖域・原生林」 2016年4月1日(金) ~ 2016年5月31日(火)
水越 武(みずこし たけし) (写真家プロフィール)
 第一部 「天と地のあいだ・日本アルプス」
第一部 「天と地のあいだ・日本アルプス」雪煙をあげる前穂高岳・日本アルプス 1979年
 第一部 「天と地のあいだ・日本アルプス」
第一部 「天と地のあいだ・日本アルプス」カールの底の巨岩・日本アルプス 1985年
田淵行男との出会い
水越武さんは1938年に愛知県豊橋市で生まれました。東三河の中心都市である豊橋は「年に一度か二度しか雪が舞うことがない」穏やかな土地柄でしたが、小学生の頃から母親と御嶽講に参加することで、山歩きに興味を抱くようになります。高校に入ると山岳部の一員として、南アルプスの山々を中心に登山に明け暮れるようになりました。
1957年に東京農業大学林学科に入学しますが、58年に中退、映画製作の仕事などをします。やがて写真家になることを志して、日本の自然写真の草分けの一人で、長野県安曇野を舞台に山岳写真と昆虫の生態写真を撮影していた田淵行男に師事しました。田淵の厳しい指導の下で、その優れた資質に磨きをかけ、1971年に独立します。以後、日本を代表する自然写真家の一人として活躍し、国際的にも高く評価されてきました。
日本アルプスからヒマラヤへ
水越さんがまず取り組んだのは、槍ヶ岳、穂高連峰、白馬岳をはじめとする日本アルプスの山々でした。四季折々の山の魅力を、そこに生きる動物や植物たちにも目を向けて細やかに捉える水越さんの仕事は、日本の山岳写真に新たな領域を切り拓きました。
既に1969年には、アラスカ・マッキンリー登山隊の一員として登頂に成功していますが、70年代以降は本格的に海外の山々の取材を開始します。特にヒマラヤのスケールの大きな自然に魅せられ、長期取材を積み重ねていきました。それらの写真は写真集『HIMALAYA』(講談社、1993年)にまとめられ、代表作の一つとなりました。
森に踏み込む
山岳写真とともに、水越さんは早くから森の環境にも強い関心を持ち続けてきました。ぎりぎりの生存条件に適応している森林限界の樹木や、伐採や環境破壊によって危機に瀕しつつある原生林に目を向け、日本列島を縦断して森を撮影し続けていきました。その成果は『森林限界』(山と渓谷社、1986年)、『日本の原生林』(岩波書店、1990年)、『森林列島』(岩波書店、1998年)といった写真集として刊行されます。生粋のナチュラリストの観察力と、登山家としての経験が活かされた力強い写真群です。
1990年代になると、水越さんの撮影の範囲は熱帯雨林にまで広がっていきます。東南アジア、中南米、アフリカと、年に2、3回の長期旅行を繰り返して粘り強く撮影を続け、2001年に写真集『熱帯雨林』(岩波書店)を刊行しました。その過程で、地球温暖化によって縮小しつつある氷河が新たなテーマとして浮上してきました。その成果をまとめたのが『熱帯の氷河』(山と渓谷社、2009年)です。
モノクロームへのこだわり
水越さんはカラー写真が全盛となった1980年代以降も、モノクロームのプリントに強いこだわりを持ち続けてきました。それは白と黒のシンプルなグラデーションに還元された世界の方が、人間の尺度を超えた山や森の環境で彼が経験した驚きや感動を、的確に、力強く伝えてくれると考えているからです。「自然の声に耳を傾け、何かを摑みたいと考えた時、いつも拠り所としたのはモノクロームの写真だった。それは自己に投影させ重ねる存在、私の生き方、そのものであったような気がする」とも述べています。水越さんの写真は、よく「求道者のような」と評されますが、そのあり方はモノクローム写真にこそ、より強くあらわれているといえそうです。
水越さんの長年にわたるモノクローム写真への探求が、見事に形をとったのが、今回展示される「真昼の星」のシリーズです。「切り立った険しい山の岩壁では、真上の黒みを帯びた青空に真昼でも星が見える」という話に由来するというタイトルからしても、このシリーズはモノクロームでなければならなかったといえるでしょう。そこには、厳しさの中に優しさやロマンティシズムが同居する水越さんの作品世界のエッセンスが、たっぷりと詰まっています。
(飯沢耕太郎)