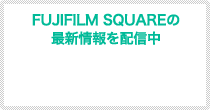- 写真展 FUJIFILM SQUARE(トップ)
- 写真展の鑑賞ガイド
- ジャック=アンリ・ラルティーグ(Jacques Henri Lartigue)ってどんな写真家?
ジャック=アンリ・ラルティーグ(Jacques Henri Lartigue)ってどんな写真家?
【FUJIFILM SQUARE 写真歴史博物館企画写真展】世界でもっとも偉大なアマチュア写真家 ジャック=アンリ・ラルティーグ作品展
開催期間:2015/11/03~2016/02/01
ジャック=アンリ・ラルティーグ(Jacques Henri Lartigue) (写真家プロフィール)
 ドラージュ車、A.C.Fグランプリ ル・トレポー
ドラージュ車、A.C.Fグランプリ ル・トレポー1912年6月26日
Photographie Jacques Henri Lartigue ©Ministère de la Culture - France/AAJHL
 従妹のビショナード、コルタンベール通り 40番地 パリ
従妹のビショナード、コルタンベール通り 40番地 パリ1905年
Photographie Jacques Henri Lartigue ©Ministère de la Culture - France/AAJHL
天才写真家のゆりかご、ラルティーグ家
ラルティーグ家は、元来、新しい発明に飽くなき好奇心を抱く血筋でした。水路測量技師だった祖父は、風や大気、地表の動く仕組みに大きな関心を寄せていた人でした。父のアンリ・ラルティーグ(1859-1953)は、若い頃、蒸気船で多くの国を旅した後、銀行家となり莫大な富を築き上げました。新聞社の社主など多くの事業を手がけたアンリは、フランスの長者番付で8番目にランクされるほどの財産家になります。8歳のラルティーグは日記に、「パパは世界のリーダーなんだ」と誇らしげに記しています。幼いラルティーグに、初めて写真の手ほどきをした父親は、ラルティーグのヒーローだったのです。
ラルティーグより4歳年長の兄モーリス(愛称ジスー)は、ラルティーグ最愛のモデルでした。ラルティーグ家のDNAを色濃く受け継いだジスーは、常に新しいことを思いつき様々な挑戦に挑んでいました。「ジスーのおかげで、ぼくは飛行機や自動車の発展について詳しくなった。ジスーはすごい発明家だった。この発明遊びをいつも指揮し、組織したのはジスーだった」。
カメラが、いまだ庶民の手の届かない高級品だった1890年代、後に世界を驚かせる写真の天才が写真を撮るための完璧な環境に生まれ育ったのは、歴史の幸福ないたずらと言えるかもしれません。
時間よ止まれ!
ラルティーグは、6歳にしてすでに「逃げ去るものたちの記録(ラルティーグは“何ものかと呼んでいた)を見つける喜び」が、自分にとって非常に重要であることを認識し、ある一人遊びを創り出しました。日々の記録をデッサンし隠す、忘れた頃に、それを再発見したときの喜びのために..,「大人たちは、もはや“何ものかに興味がない。それがあったことさえ忘れているのかもしれない。だって、その“何ものかは記憶の中にしかないのだから。でも、ぼくは大人になっても自分の書いた紙を見つけられるんだ。そして、“何ものか”があったことを忘れないでいられるんだ」。それは、時と忘却を阻止することへの初めての試みだったのです。
8歳にして、感性が人一倍豊かだったラルティーグは、兄やいとこたちと遊びながら、その幸せな瞬間を止めることのできない苦しみを自覚しはじめます。「みんなが遊んでいるのを劇場のお客さんみたいに見ているのは、とっても楽しい。でも、今日の朝、いつものようにみんなを見ていたら、ちょっと泣きそうになったんだ。そして、あることを思いついた:目を開く、そして閉じる。また開く、大きく開く。ほら!目の前のイメージをつかまえられるんだ。光も、陰も、色も!そのままの大きさで。ぼくはそのイメージをずっと持ち続けられる。この発明は素晴らしい秘密だ...」。しかし、この発明は気分次第で上手くいくときもあれば、まったくダメな時もありラルティーグを失望させたのです。
「魔法の箱」、写真との出会い
新しい技術に飽くなき関心を抱いていた父親アンリ・ラルティーグは、写真にも早くから傾倒し、1892年から自分で撮影から現像まで行うようになっていました。幼いラルティーグも、父親が現像を行う傍らで、次第に像が浮かびあがる魔法を見てすぐさまその虜になります。逃げていく幸福をとどめたいがために発明した自分の遊戯が上手くいかず病気になりかけていた息子に、父親はその遊戯を完璧にしてくれるカメラを贈ることにします。以降、ラルティーグは終生、写真を撮り続けることになりました。
動くものをとらえたい!
写真を撮りはじめた頃から、ラルティーグは動きをとらえることに大きな関心を持っていました。車、飛行機、飛ぶもの、飛び込むもの...1888年に発売されたコダック社製のカメラは、日中、明るい光のあるときなら40分の1秒で動く被写体を素早くとらえることを可能にしました。ラルティーグの嗜好に応えるように、日進月歩で進歩して行く写真技術の発展が、ラルティーグをさらに夢中にさせます。
10歳で撮影した「僕の猫ジジ」について、ラルティーグは次のように日記に記しています。
「ジジを撮るために、ぼくは絶対に間違いのないやりかたを発明した。地面に三脚を立てカメラをジジと同じ高さにセットする。ねらうのはジジじゃない。前もって、チョークで右と左に線を引いておく。ぼくが焦点を合わせるのは、この二点で区切られた空間だ。この線の間で猫が飛び上がった瞬間に、シャッターを押すだけだ。ぼくは、ちゃんと写真が撮れていることが分かっていた。ジジは、とってもすぐれたモデルだったから」。

幽霊写真
動きをとらえることに夢中になる一方、ラルティーグは、カメラという機械が創り出す様々な像の探求にも夢中になります。「カメラのシャッターを開いて、すぐに走ってカメラの前でポーズをとって自分の写真を撮ったけど、ぼくは透明人間になっていた」。この経験から生まれたのが9歳の時に撮影された「幽霊になったジスー」である。「今日、同じやり方で、昨日パパたちが話していた幽霊の話みたいな透明の幽霊を取れないか考えてみた。ジスーにシーツをかぶってもらって、レンズの前にたってもらいシャッターを切って、また閉じる。ジスーには一度いなくなってもらって、もう一回シャッターを切る。多分、きれいな幽霊の写真が出来たと思うんだ」。
70歳を目前にした写真家デビュー
ラルティーグにとって、写真はあくまで自分だけの楽しみでした。日々、撮りためた写真は自分の「宝箱」であるアルバムに貼られ大事にしまい込まれました。これらの写真を「作品」として外部に発表したり、プロの写真家として認められたい、という気持ちがラルティーグには微塵もなかったのです。
1962年、ラルティーグは妻とともに初めてアメリカ旅行へ出かけます。この旅がラルティーグの人生を一変させることになるとは、ラルティーグ自身、まったく予想もしなかったことでした。ニューヨークに立ち寄った際、知人から紹介されたフランスの写真エージェンシー・ラフォの創設者シャルル・ラドを訪ねます。表敬訪問にすぎなかったこの訪問の際、ラルティーグは幼い頃から写真を撮っていることを語り、フランスからアメリカへの長い船旅の中でラルティーグが作った小さなアルバムを見せます。ラドも儀礼的にアマチュア写真家の写真を見るつもりが、アルバムに貼られた写真を見たラドの反応は180度転換します。「これはすごい写真だ」ということを直感したラドは、ニューヨークの写真界の大立者たちに「彗星のごとくフランスから現れた新人写真家」を喧伝して回ることになります。
その一人、ラルティーグの写真に驚いたニューヨーク近代美術館(MOMA)の写真部長ジョン・シャーカフスキーは、即座に展覧会の開催を決め、1963年7月、ラルティーグ初の展覧会が幕を開けます。69歳の新人写真家の華々しいデビューでした。アメリカ人が思い描く「古き良き時代のエレガンス」を体現したラルティーグの写真は大きな評判となり、この展覧会はアメリカ、カナダの16カ所を巡回しました。さらに、ラルティーグを特集した同年11月のライフ誌が、ケネディ大統領の暗殺を報じた号と重なったことから、さらに多くの大衆の目に触れラルティーグの名前を知らしめることになりました。
1966年、ファッション写真家として名を馳せていたリチャード・アベドンのアシスタント、ヒロの招きによって、ラルティーグは再びニューヨークの地を踏みます。そこで見せた未発表だった1930年代以降の写真に感動したアベドンの尽力により「ファミリー・アルバム」の出版が決まり、この写真集によりラルティーグの名は世界的に知られることになりました。
当時のラルティーグの日記には、「ニューヨーク中が私のことを話している!何についてかって?私の写真についてだ!まったく、予想もしなかったことだ...」と書かれています。
アメリカから逆輸入される形で、本国フランスでもラルティーグの写真家としての名声は高まり続け、1979年、ラルティーグが80歳を迎えた年にネガ、写真、アルバム、日記すべてが、国有財産としてフランス政府文化省の下に管理されることになりました。